【第2回】地域バンドの誕生
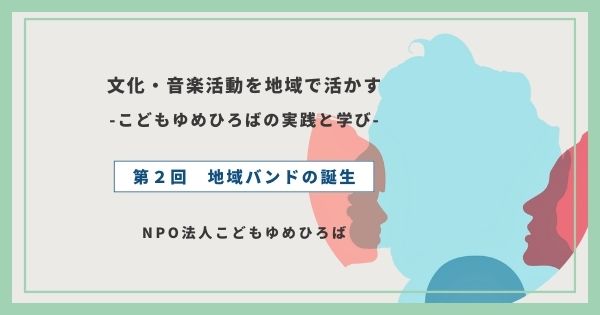
NPOが運営する吹奏楽団のかたち
— 「なら夢鹿Brass」が生まれるまで —
子どもたちに音楽の場を残したい。
その思いから私たちNPO法人こどもゆめひろばが最初に取り組んだのが、中学生を対象とした地域の吹奏楽団です。
今では「なら夢鹿(ムジカ)Brass」という名前で活動していますが、実はこの活動は、中学校からの相談がきっかけでした。
学校から地域へ、「続ける」ための相談から始まった
私たちの代表・中川が部活動指導員として関わっていた、奈良市立登美ヶ丘北中学校。
その学校から、「将来的に土日の部活動が制限される。学校では対応が難しいので、何かサポートしてもらえないか」という相談をいただいたのが始まりでした。
部活が急に減ることで、子どもたちが音楽に関わる時間が減ってしまうのでは——。
そこで私たちは、学校と連携しながら、地域で新たな吹奏楽の活動を立ち上げることにしたのです。
「中学生地域バンド」としてのスタート
まず行ったのは、中学校に眠っている使われていない楽器のメンテナンスです。蘇った楽器をたくさん用意して、3月に体験会を開催しました。
登美ヶ丘北中学校の吹奏楽部員だけでなく、他校の生徒も対象とし、初心者・経験者を問わず幅広く呼びかけました。
その後、本格的な活動を「中学生地域バンド」として開始。
奈良市立登美ヶ丘北中学校の視聴覚室をお借りして、週末の練習を行っています。
もともと吹奏楽部が活動している音楽室ではなく、別の部屋を使っているため、楽器の移動や保管にも工夫が必要です。
たとえば、毎回音楽室から視聴覚室へ楽器を運び、使った楽器は会場に在学している中学生にお願いして、週明けに音楽室へ戻してもらっています。
学校施設を使わせていただくうえで、施錠やセキュリティなどにも配慮しながら運営しています。
「なら夢鹿BRASS」という名前に込めた想い
活動が軌道に乗り始めた6月、私たちはチャリティーマルシェイベントを開催しました。
その中で、子どもたちと一緒に「この楽団に名前をつけよう」という話になり、決まったのが「なら夢鹿(ムジカ)BRASS」です。
“夢”を持って音楽に向き合い、“鹿”のように奈良の地に根ざした活動をしていく。
そんな意味が込められたこの名前には、子どもたち自身の想いも込められています。
大人が教えるのではなく、“共に奏でる”という関わり方
立ち上げ当初から課題だったのが、指導する大人の確保です。
学校の先生に代わって、地域で音楽の練習を見られる人材はそう多くはありません。
そこで私たちは「チューター制度」を導入しました。
これは、音楽を趣味として続けている大人の方々に、研修を経てサポートメンバーとして参加してもらう制度です。
チューターは“教える先生”ではなく、“隣で一緒に吹いてくれる先輩”のような存在。
子どもたちは、自然と演奏を真似したり、分からないことを気軽に質問したりしながら、自ら学ぶ力を育んでいきます。
完璧じゃなくていい。でも「続けられる場」が必要
地域での音楽活動には、場所・人・費用などの課題が常につきまといます。
でも、子どもたちにとって「続けられる場所」があることは、それだけで安心と成長の土台になります。
なら夢鹿BRASSは、まだ走り出したばかりの楽団です。
でも、子どもたちの笑顔と音が重なるたび、「やってよかった」と心から思える場になっています。
次回は…
次回は、地域の保護者や音楽経験者が中心となって立ち上げた団体を、こどもゆめひろばが伴走支援している事例(生駒エリア)をご紹介します。
“自分たちのまちでも、音楽の場をつくってみたい”——そんな声に応えた取り組みです。